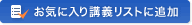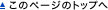- 開講元
- 機械コース
- 担当教員名
- 中野 寛
- 授業形態
- 講義 (ライブ型)
- メディア利用科目
- 曜日・時限(講義室)
- 水1-2
- クラス
- -
- 科目コード
- MEC.D433
- 単位数
- 1
- 開講年度
- 2023年度
- 開講クォーター
- 3Q
- シラバス更新日
- 2023年9月28日
- 講義資料更新日
- -
- 使用言語
- 英語
- アクセスランキング
-

講義の概要とねらい
本講義では、構造物や機械に生じる自励振動現象を扱う.自励振動発生後の挙動ではなく、発生の有無の判別に焦点を当て、線形系の不安定振動として解析を行う方法を説明する。機械に生じるさまざまな自励振動の例を挙げ、それぞれの発生メカニズムや抑制方法について学ぶ。自励振動現象のモデル化、運動方程式の導出を行い、物理的には異なる現象に見える発生メカニズムを数学的に見ることで、共通する現象に分類できることを示し、自励振動現象を体系的に捉える能力を習得する。
到達目標
本講義を履修することによって以下の能力を習得する。
(1) 自励振動と強制振動の違いを説明できる。
(2) 自励振動の発生メカニズムを説明できる
(3) 自励振動の発生メカニズムを踏まえてその抑制法を説明できる。
キーワード
自励振動、安定判別、不安定振動、負性抵抗、摩擦振動、係数励振、乾性摩擦、サージング、ギャロッピング、時間遅れ、再生びびり、クーロン摩擦、フラッタ
学生が身につける力(ディグリー・ポリシー)
| ✔ 専門力 | 教養力 | コミュニケーション力 | 展開力(探究力又は設定力) | ✔ 展開力(実践力又は解決力) |
授業の進め方
各回の講義は、ライブ型(Zoom)で行う。
必要に応じて講義開始時に資料を配布する。
授業に関係する宿題を課す。
授業計画・課題
| 授業計画 | 課題 | |
|---|---|---|
| 第1回 | イントロダクション | 身のまわりの自励振動現象の例を調べる. |
| 第2回 | 安定性解析 | 安定性解析の理解 |
| 第3回 | 負性抵抗に基づく不安定振動 | 負性抵抗に基づく不安定振動の理解 |
| 第4回 | 時間遅れに基づく不安定振動 | 時間遅れに基づく不安定振動の理解 |
| 第5回 | 非対称性に基づく不安定振動1 | 非対称性に基づく摩擦振動の理解 |
| 第6回 | 非対称性に基づく不安定振動2 | フラッタの理解 |
| 第7回 | 自励振動の抑制と講義全体の総括 | 自励振動の抑制対策の理解と講義全体の理解度確認 |
授業時間外学修(予習・復習等)
学修効果を上げるため,教科書や配布資料等の該当箇所を参照し,「毎授業」授業内容に関する予習と復習(課題含む)をそれぞれ概ね100分を目安に行うこと。
教科書
特になし
参考書、講義資料等
J. P. Den Hartog著, “Mechanical vibrations”, Dover Publications, ISBN-13: 978-0486647852
Singiresu S. Rao著, “Mechanical Vibrations”, Prentice Hall; 5th Revised, ISBN-13: 978-9810687120
日本機械学会編, “機械工学便覧 基礎編α2:機械力学”, 日本機械学会, ISBN-13: 978-4888981163
成績評価の基準及び方法
レポート(30%)と達成度確認テスト(70%)の割合で評価します。なお、対面による期末試験を実施できなくなった場合は、授業ごとに課されるレポートで成績を評価します。
関連する科目
- Mechanical vibrations (MEC.D201)
- Vibration analysis (MEC.D311)
- Rotor dynamics (MEC.D432)
履修の条件(知識・技能・履修済科目等)
機械力学(MEC.D201)、振動解析学(MEC.D311)を履修していること、または同等の知識があること。
その他
授業形態:ライブ型
質問対応・意見交換の方法:
・授業中や小休憩中にZoomのチャット機能または,直接通話を利用して質問対応および意見交換する。
・メールまたはT2SCHOLA上のQ&Aフォーラムで質問を受け付ける。