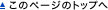- 担当教員
- 小林 憲正
- 使用教室
- 月5-6(W934)
- 単位数
- 講義:2 演習:0 実験:0
- 講義コード
- 0187
- シラバス更新日
- 2014年4月29日
- 講義資料更新日
- 2014年7月31日
- アクセス指標
-

- 学期
- 前期 / 推奨学期:3

講義
第1回 合理的選択理論 Rational Choice Theory の意義 -- ゲームの木 Game Tree を題材にして
2014年04月07日(月) 5-6時限開講
 おもしろ小論「歴史とは「たくさんの」ゲームのプレーのことである」 -- 匿名希望(51KB)
おもしろ小論「歴史とは「たくさんの」ゲームのプレーのことである」 -- 匿名希望(51KB)
サンクコストが一つのゲームであるのに対して、歴史は「今までの全ての対局の結果」であるとする解釈、なかなか明確で説得力があると思います。
しかし、この解釈でも、依然として、もし後ろ向き帰納法が可能ならば、特に歴史を学ぶ必要はないのでは?歴史を学ぶことの意義があるとすれば、ご指摘の解釈に加えて、なんらかの前提が必要と考えられます。それはなんでしょうか?
 おもしろ小論「sunk cost fallacy を回避するべく歴史から学ぶ」(121KB)
おもしろ小論「sunk cost fallacy を回避するべく歴史から学ぶ」(121KB)
sunk cost fallacy それ自体を回避するべく過去の失敗から学ぶことを、過去を学ぶ意義の一つとして提起してくれました。大変鋭いアイデアだと思います。ただし、おそらく深く考えると2つ問題点が浮かび上がってくると思います。1)過去の経験をそもそも fallacy と分類できるでしょうか?皆さんの中でも何割かの方は、本講義の話を聞くまでは、sunk cost fallacy を誤りとして認識していなかったのではないでしょうか?2)過去を学ぶ意義があるから過去を気にするのであり、いわばその副作用が sunk cost fallacy に思えます。今回頂いたアイデアでは、若干卵と鶏が逆に感じられなくもありません。
ともかくも、アイデアが秀逸と思うので、おもしろ小論と認定します。
 おもしろ小論「sunk cost fallacy の実例」(194KB)
おもしろ小論「sunk cost fallacy の実例」(194KB) 本題それ自体へのアタックは、もう少し頑張って考えて欲しかったですが、導入としての実例は秀逸と思います!
 おもしろ小論「歴史を学ぶことは合理的ではない」(23KB)
おもしろ小論「歴史を学ぶことは合理的ではない」(23KB) 逆手に取った回答。そして、グローバル経済における下手な日本型経営の弊害などのような、慣習に縛られることの弊害をわかりやすく述べていると思います。ただし、せっかくの大学の講義の小論なので、「後ろ向き帰納法」との関係性をもう少し直接議論して欲しかった。アイデアの方向性と初回ということで、若干おまけです!
 優秀小論「歴史を学ぶことの意義」(71KB)
優秀小論「歴史を学ぶことの意義」(71KB)
小論としての体裁が整っていると思います。考えうる意義を3種類説得力のある形で類型化し、一つ目の「楽しいから」ということ以外、あまり意味がなさそうなことを論証しました。特に3つ目の要因が個人的にはツボです。いわゆる voter's paradox ということとも関連するのですが、国家の歴史と個人の意思決定になんの関係があろうか?ということです。皆さんは国家と個人の無関係性を肌で強く感じているため、かつてに比べてどんどん投票率が低くなっていると思います。
ただし、講義でもレポートの書き方の作法の説明で申し上げましたが、講義で紹介した「歴史」という用語の使い方は明らかに個人史も含みます。よって、論点3については、実はかなり題意と独立の用語の使い方になってしまっていますね。
初回で、マナーを説明する前だったので、おまけ気味ですが、優秀小論と認定します。
講義
第2回 不確実性下の意思決定 Decisions under Uncertainty
2014年04月14日(月) 5-6時限開講
 Lecture Note(191KB)
Lecture Note(191KB)
Keywords:
不確実性 uncertainty
支配戦略 dominant strategy
Max-Min 戦略 max-min strategy
リスク risk
期待効用 expected utility
完全情報の価値の期待値 expected value of perfect information (EVPI)
感度分析 sensitivity analysis
比較静学 comparative statics
 おもしろ小論「知は力なり」の定理の証明 -- 匿名希望(178KB)
おもしろ小論「知は力なり」の定理の証明 -- 匿名希望(178KB) 「おもしろい」っていうのとジャンルが違いますが、10点相当の小論のラベルを「おもしろ小論」と呼んで紹介します。本小論では、「知は力なり」という定理の証明を、不確実性の状態集合が可算の場合に、厳密に数学的帰納法で行ってくれました。大変クリアなので、皆さん定理の理解のたしにしてください。
 おもしろ小論「max-min 戦略について」(24KB)
おもしろ小論「max-min 戦略について」(24KB) 「支配戦略がある場合は、それが max-min 戦略にもなる」という命題に気づいたのはナイスです。
 おもしろ小論「病は気から」(23KB)
おもしろ小論「病は気から」(23KB)
「論証」という観点からすると、明らかに弱すぎるのですが、アイデアが大変興味深いので、皆さんにご紹介します。
常に EVPI > 0 にもかかわらず、告知しないことが時には良さそうであることの要因を2つ挙げました。ひとつは、末期の病気の時、選択肢の幅がすごくせまそうなこと。もう一つは「病は気から」です。
一つ目の「選択肢の幅が狭い」ことについては、直感的にはすごく説得力がありますし、おそらく応用例もたくさんあると思います。しかし、こと、告知問題について言えば、狭い選択肢の中でも「すごく重要な」意思決定があると思います。例えば、告知されない末期患者は遺言も書けないかもしれない。勝手に延命治療を選択されて、最後の家族旅行もできないかもしれない。これが幸せでしょうか?
2つ目については、着眼点は大変よろしいと思います。しかし、せっかく EVPI が数学的に定式化されているのだから、これが EVPI > 0 と「どう」矛盾しそうなのか、はたまた矛盾しないのか、もっと明確に、可能であればある程度モデル的に議論してください。
 優秀小論「恋は盲目」(32KB)
優秀小論「恋は盲目」(32KB) 恋は Lecture 2 で扱ったように合理的でないのでは?という鋭い「着眼点からの」ツッコミを個人的経験という強力な「論拠」に基づき入れました。極めてコンパクトですが、論証としてのフォーマットが実にしっかりしているので、今年度の初期のエッセーということで、おまけ気味に優秀小論と認定します。
講義
第3回 決定の木 Decision Tree と 完全情報ゲーム Extensive Games with Perfect Information
2014年04月21日(月) 5-6時限開講
 優秀小論「Twitter でのタグ濫用について」(87KB)
優秀小論「Twitter でのタグ濫用について」(87KB)
SNS とりわけ Twitter 「一般」における発言の意思決定要因をベネフィットとコストに分けました。それを大前提とした上で、今回の「合理的思考の技術タグ」の濫用という具体性を加味して、三段論法チックに、それぞれを極めて具体的に論じてくれました。
(EVPI の証明のレポートを除き)今年度初の非の打ち所のない完璧なレポートだと思います。
皆さんには、わかり易い文章の書き方の模範として、ぜひとも参照してほしいと思います。大言壮語的に言えば、合理的思考の技術っぽいものの見方が、いかにわかりやすく状況を整理できるかってことが体感できる模範例になっていると思います。
 おもしろ小論「second price auction について」(61KB)
おもしろ小論「second price auction について」(61KB)
second price auction の定式化と支配戦略均衡を求めるところまでは、かなりよろしいと思います。大変だったでしょう。お疲れ様でした。
ただし、東工大生には数学(数式)という武器があるでしょう。
確かに一般的な定理の証明というテーマに比べて、今回のような応用問題では数式を使うメリットはだいぶ減りますが、それでも「コンパクトな表現」というメリットはかなりあると思います。それぞれの入札額を a_i みたいな感じで、素直に利得を定義すれば、かなり行数や場合分けの数も節約でき、場合分けがもれなくだぶりないこともチェックしやすいのではないでしょうか?
後半、他者の入札額を知らない効果については、ハードル高すぎ(ちょっと反則気味)だったかもしれません。講義中で頭の体操とすることにします。
以上を鑑み、よりコンパクトに記号化する、後半の問を答えなおしてもらうってことをテーマに、引き続き優秀小論を募集します。
 優秀小論「恋愛と合理性」(158KB)
優秀小論「恋愛と合理性」(158KB)
教員のアップロード・ミスで、順序が前後してしまいましたが、Lecture 4 のおもしろ小論の修正版です。査読・修正システムが最大限うまく機能した結果(と私は思いたい:)を皆さんに鑑賞してもらいたいと思います。
なお、内容について一箇所コメントしておけば、異性の個性によって最適解がことなることは、講義全体を通じて「合理性」に矛盾するかどうかは、これから判定してください。少なくとも、講義のこれまでの内容に照らし合わせれば、合理的選択をする材料、すなわち効用関数を十分に定義する材料が揃っていないことについて同意します。
元のバージョンから申し上げていますが、大変素晴らしいレポートだと思います。
講義
第4回 標準形ゲーム Normal-Form Games
2014年04月28日(月) 5-6時限開講
 Lecture Note(202KB)
Lecture Note(202KB)
Keywords:
標準形ゲーム normal-form game
利得双行列 payoff bimatrix
最適応答 best response
囚人のジレンマ prisoner's dilemma
チキン chicken (タカハト hawk-dove)
支配戦略均衡 dominant strategy equilibrium
メカニズム・デザイン mechanism design (遂行理論 implementation theory)
直積順序 product order
パレート効率性 Pareto efficiency
社会的ジレンマ social dilemma
共有地の悲劇 the tragedy of the commons
タダ乗り問題 free rider problem
 おもしろ小論「恋愛と合理性」(161KB)
おもしろ小論「恋愛と合理性」(161KB)
恋愛の主要な要素を抑えて、それぞれに結構合理的選択が絡んでいそうなことを論じた大変素晴らしいレポートです。20点進呈したいところですが、あえて改善点を提示して、おもしろ小論と分類しておきます。余力があれば、修正・再提出ください。
まず、科学の世界は、早い者勝ちと引用が基本中の基本です。既に優秀小論として「恋は盲目」の小論があります。よって、少なくとも、本講義というコミュニティーの中では、「恋は盲目」の論文は主要文献となると考えてください。主要文献を無視して同じテーマについて小論を展開することは、不勉強とみなされることがあります。是非、「恋は盲目」の問題についてどう考えるのか、引用の上、リアクションをお願いします。(もしくは、「本論文では別の側面を議論する」というようなリアクションもありです。)加えて、インボルブという専門用語らしきものも使っていらっしゃるので、是非、この考え方をとってきた元の文献などあれば、正確に引用してください。
あと、短い論文ではありますが、セクションや段落の作り方、論文の流れ、など構造をさらにわかりやすい作りにすれば、より読みやすくなるでしょう。著者本人にとっても、自分の考えを整理することの助けになると思います。
ともかくも、ちゃんとコメントしたくなる素晴らしい小論でした。
 おもしろ小論「知は力なり と告知問題」(246KB)
おもしろ小論「知は力なり と告知問題」(246KB)
本年度初の本格的にモデルを使った小論といえるかもしれません。
ただし、モデルの使い方に問題があります。
まず、表1ですが、情報の価値は「情報取得の意思決定」という意思決定問題の情報の価値を測定したものではそもそもありません。一般のリスク下の意思決定問題にあまねく適用できる概念です。なので、本小論における応用例では、不確実性の状態集合は
\Omega = { 重病でない, 重病である }
選択肢は、
A = { 家に帰る, 入院して治療を続ける }
みたいに設定するのが素直です。
(上記は、アイドルの恋愛事情について知ることに当てはめるとどうなるでしょうか?練習問題として考えてみてください)
このような患者の一般の意思決定を踏まえて、余命を知ることの効果を測ったのが EVPI であると言えます。
後半の cost は、講義で扱ったコストとは性格が異なりますが、おそらく問題のコアでしょう。前回講義分に既にアップしてあります「病は気から」の小論に密接に関係するものと思われます。(ちゃんと引用してください!)「病は気から」の小論では、まったくモデル化しないで曖昧な議論を展開しているように見えるので、本論文で改めてモデル的にちゃんとかんがえるということが、限界貢献 marginal contribution であると位置づけることができるわけです。
初の本格的なモデルに基づくレポートなので、甘めにおもしろ小論と認定します。やる気があれば、是非、優秀小論へ向けて修正をチャレンジしてみてください。
 優秀小論「ムカデゲームにおいて相手を自然であるとみなしたプレーの効果」(1193KB)
優秀小論「ムカデゲームにおいて相手を自然であるとみなしたプレーの効果」(1193KB)
相手のプレーを単なる自然であると想定するという結構大胆なプレースタイルについて調べました。比較静学分析的にすべての場合を調べつくした、小論っていうレベルじゃなく、ちょっとした論文って感じのレポートです。
せっかくすごいレベルなんで、さらに改善点を申し上げましょう。世界の一流誌の良質な論文はおしなべて概要 Abstract と導入 Introduction が極めて重要です。いわば論文のメークに相当します。あなたは論文のなにをアピールしたいんですか?膨大な情報砂漠の中で、あなたの論文をまじめに読んでほしいためには、最大限アピールが必要です。
本論文で言えば、膨大な比較静学分析の結果、結局、定性的にどういう傾向のことが言えましたか?
学部教養講義の1レポートという性格上、既に現時点で十二分に優秀小論のレベルに達していますが、時間とエネルギーがありましたら、是非、本論文の要約をご自身の論文執筆トレーニングを目的としてお送りください。
 あと一歩!「機会費用について」(154KB)
あと一歩!「機会費用について」(154KB)
留学についての実例は、なかなか素晴らしいと思います。ただし、後半のように選択肢がかなり明確に書き尽くせているように見える場合は、あえて「機会費用」という考え方を使うまでもなく、木そのもので良さそうです。「寝る」というよりも、自由時間で半無限の選択肢がある場合みたいなときに適したツールが機会費用なのです。
講義中でも申し上げましたが、「調べる」なりして、勉強してみるのはいかが?
あと、漢字変換は気をつけよう!
 優秀小論「タカハトと情報の価値」(37KB)
優秀小論「タカハトと情報の価値」(37KB)
まず、将棋は、やはり先手が有利であるといわれています。(数学的に証明されているわけではありません)将棋とタカハトは本小論の問題設定で異なるゲームであると言えるでしょうか?
前半は、なんだか相当いい線いっている感じがします。ただ、もう一歩「後ろ向き帰納法」との関係性を深く追求してみましょう。特に、1ページ目の下の段落が先手・後手どっち視点なのかわかりにくい。この辺を整理すれば、かなり良い方向性で議論している気がします。
後半は、利得をいじって、さらに再分配までするという、かなりアクロバティックなアイデアで比較静学を行いました。アイデアはほんとうに面白いので、利得をいじった効果と再分配の効果をそれぞれもう少し丁寧に議論すれば、より説得力がましたことでしょう。
後半の比較静学分析のアイデアが大変秀逸なので、甘めですが、優秀小論と認定しておきます。
講義
第5回 ナッシュ均衡 Nash Equilibrium
2014年05月07日(水) 5-6時限開講
 Lecture Note(183KB)
Lecture Note(183KB)
Keywords:
定常状態 steady state
ナッシュ均衡 Nash equilibrium
解 solution
安定性 stability
誘引両立性 incentive compatibility
逸脱 deviation
不動点 fixed point
均衡選択 equilibrium selection
調整 coordination
強い均衡 strong equilibrium
自己破壊的予測 self defeating prediction
自己言及 self reference
小論テーマ候補:
- 各自の専門分野における興味深い理念型を紹介せよ。
- 社会に関する言説・説明・予測を本や新聞などから引用しつつ、ナッシュ均衡の基準に照らし合わせて、この言説を社会の十分数の人が信じた場合に、その言説が自己破壊されないか検討せよ。
講義
第6回 展開形ゲームの標準形表現
2014年05月12日(月) 5-6時限開講
 Lecture Note(252KB)
Lecture Note(252KB)
結果 Outcome
標準形表現 Normal-Form Representation
部分ゲーム完全ナッシュ均衡 subgame-perfect Nash equilibrium (SPNE)
信憑性のない脅し incredible threat
コミットメント commitment
チェーンストアゲーム chain store game
チェーンストアパラドックス chain store paradox
前向き帰納法 forward induction
精緻化 refinement
小論テーマ候補:
・代理人のようなコミットメントの工夫について、調べたり、自分の生活での実例を分析したりして、議論せよ。
・後ろ向き帰納法 については、突っ込みどころを簡単に紹介した。
同様に、前向き帰納法の突っ込みどころがあれば、議論せよ。
講義
第7回 混合戦略 Mixed Strategy と相関均衡点 Correlated Equilibrium
2014年05月19日(月) 5-6時限開講
 Lecture Note(361KB)
Lecture Note(361KB)
混合拡張 mixed extension
混合戦略 mixed strategy
純粋戦略 pure strategy
混合戦略ナッシュ均衡 mixed strategy Nash equilibrium
相関均衡点 correlated equilibrium
 Battle of the Sexes の混合戦略について分析した Mathematica ソース・ファイル(10479KB)
Battle of the Sexes の混合戦略について分析した Mathematica ソース・ファイル(10479KB)
小論テーマ候補:
・2 * 2 ゲームでの混合戦略にまつわる Mathematica の簡単なプログラムを組んでみました。
OCW に Mathematica のソース・ファイルの pdf をアップしました。
このソース・ファイルを直接 Mathematica で動かすか、自分で得意の言語でプログラムを組むなり、手計算なりで、様々なゲームの混合戦略の組から得られる
-- 効用可能集合 utility possibility set (UPS) と
-- 混合戦略均衡
を比較静学分析的に探って、定性的な洞察を得てみてください。
なお、教員はプログラム音痴なので、C など Mathematica 以外の言語を使う場合、アウトプットは素人にもわかりやすく説明お願いします。
注意 -- 順序関係が同じでも、効用の定量的な大きさが、結構定性的な数理的性質に影響します!
・混合戦略均衡点の現実での適用事例を紹介し、議論してください。
(あからさまに、講義で紹介された事例と酷似したものは点数が出にくいと思ってください)
・相関均衡点を達成するためのシグナルはコイントスとは限りません。
何かのシグナルを得たら、複数のナッシュ均衡のどれかをプレーするというやり方は全て相関均衡点となります。
社会や自分の周りで相関均衡点の方法が使われいてる事例があれば、紹介してください。
 優秀小論 -- Battle of the Sexes の混合戦略 UPS を解析的に求める(341KB)
優秀小論 -- Battle of the Sexes の混合戦略 UPS を解析的に求める(341KB)
どなたかが言っていたけど、数学ができる人はズルい :)
本小論は、概形を講義で紹介した Battle of the Sexes の UPS を解析的に求めました。ゲーム理論の有名な教科書に載っている手法に比べて独自の工夫をこらしています。対称性を考慮して、45度線が縦軸となるべく座標系を回転させて解析しています。
改善点:
・せっかく対称性に気づいたのだから、さらに踏み込んで、man の M, B の順序を入れ替えれば対称行列になったでしょう。
・u* の工夫の替わりに、p + q = s, p q = t と置き換える方が、より素直な対称性の活用の仕方であったと言えそうです。
いずれにせよ、対称2*2ゲームの混合戦略プロファイルの UPS を求める手法としては、相当普遍性の高そうな視点を提供してくれたということからも、文句なく、優秀小論となります。
 優秀小論アップデート・バージョン -- Battle of the Sexes の混合戦略の UPS(366KB)
優秀小論アップデート・バージョン -- Battle of the Sexes の混合戦略の UPS(366KB)
p, q の対称性を考慮して、より見やすい式に修正してくれました。
u* の方は、小林の方の知識不足だったようです。プロの論文の査読・修正システムでも、論文の筆者の方が正しく、査読者の査読のほうが読みが足りないということもあります。ただし、u* という記号の意味をもう少しわかりやすく地の文で説明くださっても良かったかもしれません。(査読のやりとりでも、御自身でおっしゃっていましたが、地の文でこれからやることを説明した上で、u それ自体を記号に用いても良さそうです)
講義
第8回 繰り返しゲーム Repeated Game
2014年05月26日(月) 5-6時限開講
 Lecture Note(220KB)
Lecture Note(220KB)
割引利得 discounted payoff
割引因子 discounted factor
割引現在価値 net present value (NPV)
双曲線割引 hyperbolic discounting
平均利得 means payoff
公的混合 public randomizing
達成可能な利得プロファイル feasible payoff profile
個人合理的 individually rational (enforceable)
制裁 punishment
オートマトン automaton
マルコフ性 Markovian property
トリガー戦略 trigger strategy
フォーク定理 folk theorem
完全フォーク定理 perfect folk theorem
epsilon-均衡 epsilon equilibrium
小論テーマ候補:
・講義ノートを参考にして、小論テーマ「我々はなぜ歴史を学ぶのか?」を再考せよ。
・繰り返しゲームとフォーク定理が現実の意思決定状況での適用で有効となるためには、各種仮定が重要となる。(まあ、全てのモデルで、同じことが言えるけどね :)この重要な仮定について考えてみよう。
特に、グローバル化時代なんていう状況も、応用例の一つになるかも。
・講義で扱った実例では、完全フォーク定理とナッシュ・フォーク定理の違いがわかりづらかった。実際には、ナッシュ・フォーク定理では、いろいろな意味で制裁にコストがかかるため、制裁に信憑性がなくなってしまうこともあり得る。そうした状況の実例をステージ・ゲームを具体的に特定することによって議論せよ。
講義
第9回 チープトーク Cheap Talk
2014年06月02日(月) 5-6時限開講
 Lecture Note(217KB)
Lecture Note(217KB)
小論テーマ候補:
・恋愛において、なぜ愛の告白をする方が、自分と付き合うメリットをプレゼンするよりも効果的なのだろうか?
チープトークをはじめとして、これまで学んだことを総動員して、議論せよ。
講義
第10回 不完全情報ゲーム Extensive Games with Imperfect Information とシグナリング Signaling
2014年06月09日(月) 5-6時限開講
 Lecture Note(189KB)
Lecture Note(189KB)
小論テーマ候補:
・
講義
第11回 公理論的交渉理論 Axiomatic Bargaining
2014年06月16日(月) 5-6時限開講
 bargaining(149KB)
bargaining(149KB)
小論テーマ候補:
・日本と外国の交渉の事例や、自分がこれまで関わってきた話し合いなどを、公理的交渉理論に照らし合わせて検討してみよう。
講義
第12回 測定理論 Measurement Theory と 選好 Preference, 効用 Utility I
講義
第13回 測定理論 Measurement Theory と 選好 Preference, 効用 Utility II
2014年06月30日(月) 5-6時限開講
講義
第14回 社会規範 Social Norms
2014年07月07日(月) 5-6時限開講
講義