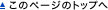- 使用教室
- 月5-7(原輪 North No.2 5F-571)
- 単位数
- 講義:2 演習:1 実験:0
- 講義コード
- 71031
- シラバス更新日
- 2008年4月2日
- 講義資料更新日
- 2008年4月2日
- アクセス指標
-

- 学期
- 前期

講義概要
原子炉では中性子が媒介する核分裂の連鎖反応により大量のエネルギーを発生している。核分裂の空間的分布や時間変動が重要な特性となる。このような事象を扱うのが原子炉理論である。
原子核工学の中心を成すのが原子炉であり、その理論が原子炉理論であることから、原子核工学専攻の学生には必須の科目としている。
核反応の知識や線形微積分方程式に関する基礎知識を使うが、これらを学んできていない学生にもわかるように講義がおこなわれる。
この講義を修了すると、簡単な原子炉の設計ができるように考えて内容が組み立てられている。後学期に原子力設計工学演習を履修するものはこの講義をとっておく必要がある。
講義の目的
核エネルギーシステム及び核物質変換システムの基礎について学ぶとともに、その中心となる中性子の発生、反応、輸送、利用について学習する。特に中性子の輸送は解析手法を駆使することになるので、演習を通じてその取扱いを習得する。
講義計画
1. 原子核物理と中性子工学の歴史
2. 素粒子・原子核とエネルギー、核反応
3. 原子核チャートと核分裂・核融合
4. 中性子による核反応(反応の種類と特徴、中性子束と断面積)
5. 中性子による核反応(散乱、核分裂)
6. 核融合中性子工学と遮蔽
7. 連鎖反応(連鎖反応と臨界、実効増倍係数)
8. 原子炉とその原理(熱中性子炉、高速炉)
9. 中性子の輸送(中性子輸送方程式、中性子減速方程式)
10. 中性子の輸送(中性子拡散方程式、多群方程式と少群方程式)
11. 原子炉の時間的変化とその制御(遅発中性子、各種の反応度フィードバック)
12. 原子炉の時間的変化とその制御(キセノンの影響、燃焼)
13. 中性子の発生と計測
14. 未来核平衡社会(核種バランスと中性子バランス、毒性バランス、一般的諸問題)
15. エネルギー発生以外の中性子利用
教科書・参考書等
【テキスト等】
H. Sekimoto, ""Nuclear Reactor Theory,"" COE-INES, Tokyo Institute of Technology, 2007
必要に応じ資料を配布する。
【参考書】
J. J. Duderstadt, L. J. Hamilton,“Nuclear Reactor Analysis”, John Wiley & Sons, 1976.
(訳本:原子炉の理論と解析(上下)、成田正郎・藤田文行共訳、現代工学社、1980 1981)
関連科目・履修の条件等
本科目は西暦奇数年度は英語(次頁参照)、偶数年度は日本語で開講するが、どちらも同一科目とみなすので両方の単位を修得することはできない。
成績評価
宿題及び期末試験
担当教員の一言
原子核工学の柱となる科目で、かつ他の科目とは非常に異なる科目であるので、原子核工学を学ぼうとする学生はぜひ履修して欲しい。